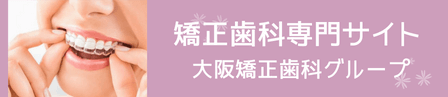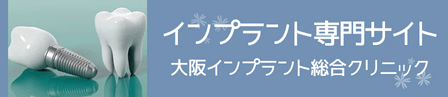歯槽膿漏とはどんなもの?

歯槽膿漏(しそうのうろう)という言葉を昔のCMで見かけたことがありませんか。実際に歯槽膿漏とはどのような状態か、歯槽膿漏になる原因、症状、対処法、予防習慣について、詳しくご紹介いたします。
歯槽膿漏とは
歯槽膿漏とは、歯周病が進行して歯茎(歯肉)や歯を支える骨(歯槽骨)が破壊されている重度の状態です。昔はよくこの名前が一般的でしたが、最近では、歯周病と呼びます。日本人の約80%がかかっていると言われ、年齢を問わず、自覚症状がないのが特徴です。歯槽膿漏まで悪化すると歯がぐらつき、最終的に歯が抜け落ちてしまうこともあります。
歯周病は軽度の時には自覚症状が少なく、中度や重度になり気づき、自覚症状が出た頃には進行していることが多いです。また、歯周病を引き起こした細菌が、血管から全身へ回ってしまうと、全身疾患(アルツハイマー、動脈硬化による心疾患、脳梗塞など)になる可能性があります。歯周病と気づいたら早めに対処することが重要です。
歯肉炎・歯周病・歯槽膿漏の違い
歯肉炎から歯周病になり、更に重度になると歯槽膿漏に進行します。
歯肉炎(歯と歯茎の境目が4mm以上で歯槽骨が溶けていない)
歯肉が赤くぷくっと腫れたり、歯磨きする度に出血するという状態です。歯肉に限った炎症が起きています。
歯周病(歯周ポケットの深さが3mm以上が軽度、4mm以上が中度、6mm以上は重度。歯槽骨が溶けている)
歯肉の腫れが酷くなり、冷たいものがしみたり、歯茎下がりが起きる状態です。歯肉のみではなく、歯の周りにある歯根膜や、歯を支えている歯槽骨にまで影響が広がっています。
歯槽膿漏
歯周病が進行し、歯肉から強い口臭がして、歯がグラグラと揺れているような状態です。歯を支える歯槽骨が溶け切ってしまっていて、歯が動揺します。専門的には重度歯周病と呼び、歯の保存が難しい段階です。
①歯肉が健康な状態 → 歯茎が引き締まり、ピンク色をしている
②歯肉炎(初期) → 歯茎が赤く腫れ、歯磨き時に出血する
③歯周炎(中期) → 歯茎が後退し、歯がぐらつき始める
④歯槽膿漏(重度歯周病) → 歯を支える骨が溶け、膿が出る・歯が抜ける
歯槽膿漏の主な原因とは
歯槽膿漏になってしまう原因はさまざまです。
プラーク(歯垢)や食べかすが多い
歯垢(プラーク)は細菌の塊です。食後に歯磨きを行わなければ、食べかすも口腔内に存在します。食べかすを餌にした歯垢が歯と歯茎の境目に溜まると炎症を引き起こし、歯槽膿漏の原因となります。食後に正しく歯を磨けていないと、歯垢が残りやすく、歯周病が進行しやすくなります。
歯石の形成
唾液に含まれる成分によりプラークが硬化して歯石になると、歯周ポケットに沈着します。歯周ポケットがツルツルしていないため、引っかかりが出来て細菌がさらに増殖しやすくなり、歯槽膿漏のリスクが高まります。
喫煙
紙タバコや加熱式タバコに含まれるニコチン成分は歯茎の血流を悪化させます。プロピレングリコールやグリセリン含有の電子タバコは、加熱すると発がん性物質を生成する言われており、お口の健康について疑問が残ります。いずれにしろ喫煙は免疫力を低下させ、血液の流れを悪くするため、歯槽膿漏の進行を早めます。
ストレスと免疫力の低下
ストレスや睡眠不足が日常的に続いていると免疫力が低下します。自律神経の乱れにより血液の流れ、歯茎が炎症を起こしやすくなります。
遺伝的要因
家族に歯周病の人が多い場合、歯槽膿漏になりやすい体質である可能性があります。
歯槽膿漏の症状とチェック方法
歯槽膿漏は、痛みが少ないまま進行することが多いため、口腔内の状態を定期的にチェックすることが大切です。
歯槽膿漏の主な症状
- 歯茎が健康なピンク色ではなく赤くなっている
- 歯磨きや食事で出血する
- 口臭が強くなる
- 歯がぐらつく
- 歯茎から膿が出ていたりできものがある
セルフチェック方法
- 鏡で歯茎の色を確認し、赤く腫れていないか
- 綺麗に洗った指で歯を軽く押してみてぐらつきがないか
- デンタルフロスの臭いを嗅いで、強い臭いがしないか
症状が1つでも当てはまり、セルフチェックで引っかかる項目があった場合は、クリニックでの診察の受診をおすすめします。
歯槽膿漏の治療法と改善方法
歯槽膿漏の治療は、進行度によって異なります。早期発見・早期治療が必要です。
① スケーリング(歯石除去)
歯茎より上についている歯石を歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)と呼びます。それを取り除くことで、歯周病の進行を抑えます。
② ルートプレーニング(歯根のクリーニング)
歯周ポケット内に付着した歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)や歯垢を除去し、歯の根元の表面を滑らかにします。滑らかにすることで歯垢や歯石がつきにくくなります。
③ 抗菌療法(薬の使用)
歯周膿瘍(ししゅうのうよう)という段階に進んでいる場合は、膿が溜まって痛みや発熱が起きることがあります。その場合はクラリスロマイシンなどの抗菌薬を使用して細菌を減らします。
④ 歯周外科手術
重度の場合は、手術によって感染した組織を除去し、歯周ポケットを浅くする処置を行います。
- 歯茎をメスで切開して歯根に付着した歯石を取り除くフラップ手術
- 歯周組織をGBRやエムドゲインで組織を再生させる歯周組織再生療法
⑤ブルーラジカル治療
過酸化水素とブルーのレーザー照射のラジカル殺菌が行える重度の歯周病への治療法です。厚生労働省より認可を受けた器械を使用し、切開や縫合が不要であるため、外科手術に比べて回復が早いです。ただし、光線過敏症や無カタラーゼ症の方、ペースメーカーをご使用の方はこの治療法を行えません。当院では2025年3月中旬頃よりブルーラジカル治療を開始いたします。
歯槽膿漏を予防するための習慣
歯槽膿漏を防ぐには、毎日のセルフケア定期的な健診を組み合わせることが欠かせません。生活習慣の改善と適切な口腔ケアでリスクを減らすことができます。
① 正しい歯磨きを習慣化
歯と歯茎の境目を意識してやさしく丁寧に磨きましょう。毎食後が理想ですが難しければ一日に2回、3分以上の歯磨きを心がけるようにしてください。就寝前にはデンタルフロス、歯間ブラシ、タフトブラシを併用しましょう。
② 定期検診を受ける
3~6ヶ月に1回クリニックへ通院し、定期検診を受け、早期発見・早期治療に努めましょう。その際に専門的なクリーニングをしてもらい、バイオフィルムや歯石除去を定期的に行えれば、歯周病を防ぐことができます。
③ 生活習慣を改善する
ビタミンCやカルシウムを摂取すると歯周組織の新陳代謝が活性化されます。なるべくバランスの良い食事を摂りましょう。喫煙習慣がある方は歯周病のリスクを高めてしまっているため、なるべく禁煙できるようにしてください。免疫力の低下を防ぐために、ストレスを溜めないようにし、リラックスする時間を持つようにしましょう。
まとめ
歯槽膿漏は、進行すると歯を失うリスクのある深刻な病気です。痛みがないから大丈夫と放置せず、早めのケアと治療が肝心です。
- 日々のセルフケアをしっかり行うこと
- 定期的に検診を受けること
- 生活習慣を改善して歯茎の健康を守ること
これらに注意して歯槽膿漏を防ぎ、患者さん自身の健康な歯や歯茎を維持しましょう。